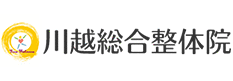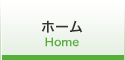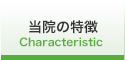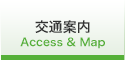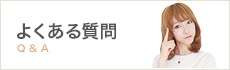カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2023年4月 (1)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (5)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (7)
- 2016年12月 (8)
- 2016年11月 (11)
- 2016年10月 (13)
- 2016年9月 (11)
- 2016年8月 (10)
- 2016年7月 (25)
- 2016年6月 (19)
- 2016年5月 (8)
- 2016年4月 (9)
- 2016年3月 (9)
- 2016年2月 (6)
最近のエントリー

HOME > 院長ブログ

院長ブログ
川越市 新河岸の整体院 【カラダの不調を知らせるサイン「手のしびれ」】

手のしびれには、一過性症状と慢性症状の2つの症状とがあります。
整体の見地からは、カラダのゆがみや筋肉の緊張や自律神経の乱れから起こる血行障害などが考えられます。
この他、さまざまな病気が原因となってしびれが出ることもあるので、まずは病院で早めに検査をしましょう。
異常が見当たらない、とくに大きな問題はないと診断があったのでれは、上記したような整体がお役に立てる場合も多々あります。
あきらめずに、ご相談下さい!
今回は、手のしびれの症状や原因などについてお伝えします。
ご参考下さい。
手のしびれについて
手のしびれには、しばらく時間をおけばおさまる一過性のものと、いつも症状を感じる慢性症状とがあります。
一過性の場合は、同じ姿勢が続いたり、不自然な姿勢で寝違えたりした時に発症する傾向があります。
それに対して慢性症状の場合は、なんらかのカラダの不調が発しているサインであることが多く、原因をつきとめる必要があります。
また、どちらの場合も脳の一部の血流が悪くなって発症している可能性も考えられます。
しびれの感じ方
しびれの感じ方場合3種類に分けられ、運動麻痺、異常知覚、感覚鈍麻とに分けられます。
運動麻痺
しびれによって手が動かしにくくなって、運動機能障害によって起こることが多い症状です。
異常知覚
チクチクしたり、ビリビリ、ズキズキといった感覚で、ときに痛みをともなって現れる症状です。
感覚鈍麻
しびれによって、手足の感覚が麻痺している状態を指します。
熱さや冷たさ、痛みを感じにくくなる、こともあります。
症状を伝える際に確認しておきたいポイント
しびれやしびれを伴う痛みを放っておくと、その原因がわかりづらくなってしまいますので、しびれに関する以下の項目を明確にしておきましょう。
・しびれているのは手のどの部分か
・どのようなしびれの感じ方をしているか
・いつごろからしびれているか
・どのように手を動かすとしびれを感じるか
・しびれにともなった他の症状があるか
以上の項目を明確にしておくことは、診察や整体を受けるときに役立ちます。
なにが原因で、どのように治療していけばよいのかの判断につながるでしょう。
・安静にしていればしびれが治まる
なども、参考材料のひとつとなるので、お伝えてください。
脳や脊髄のダメージが原因のしびれについて
手のしびれが起こる原因は1つではありません。ひどい場合は、脳血管の出血などで脳細胞に血液が行き渡らなくなっているために起こるしびれ、脳からの指令を伝達する神経の束である脊髄の病気などでも、手のしびれが発症します。
また、整体の分野では背骨や椎間板による神経の圧迫、腕や指の動きを支配する末梢神経の圧迫、ストレス、自律神経の乱れによる筋肉の緊張によって起こる肩こりや筋肉痛などの血行不良によっても、手のしびれを感じることがあります。
脳の病気である場合、吐き気や嘔吐、頭痛、ろれつが回らないなどの症状があります。
脊髄腫瘍や脊髄損傷など脊髄の病気、頚椎症性神経根症や頚椎椎間板ヘルニアなどの椎骨・椎間板による神経の圧迫、胸郭出口症候群や手根管症候群などの末梢神経の圧迫、血行不良によって起こったと考えられる手のしびれは、まず整形外科で診察を受けましょう。
病院での治療でなかなか良い変化が得られない場合、 カラダのゆがみが強く影響しているかもしれません。
川越総合整体院へお気軽にご相談下さい!
(川越総合整体院)
2016年12月18日 07:49





川越市 新河岸の整体院 【眼精疲労からのめまい】

今回は、めまいの症状や原因の違いから、眼精疲労とめまいの関係性についてお伝えしたいと思います。
カラダのどの部分の不調かによって、めまいの種類が変わってきます。
ご参考下さい!
眼精疲労が続くと、めまいを引き起こす事もあります。
めまいについても、カラダの不調を知らせてくれる大切なメッセージです。
もし、めまいを発症した場合は、カラダを休ませて、それでもなかなか改善されない場合は先ず、病院を受診してみましょう。
検査で特に異常が見当たらない場合は、カラダのゆがみから起きてるかもしれません。
そんな時は、川越総合整体院へご相談下さい!
めまいが起こるその理由とは?
私たちは脳や耳の機能によって、カラダのバランスを保つことができています。
その機能に少しでも異常が生じたり、変化が起きると、その結果としてめまいが現れます。
またカラダのどの部分に異常があるかで、めまいの症状も変わってきます。
めまいの種類と原因について
★グルグルと目がまわる「回転性のめまい」について
周りがグルグルと回っているように見えたり、自分自身が回っているような感覚に陥るめまいを「回転性のめまい」と呼びます。
回転性めまいは急に起きて、めまいと同時に吐き気やおう吐、耳鳴り、耳が聞こえづらくなるなどの症状を伴います。
回転性のめまいの多くは、三半規管の異常が挙げられます。
★カラダがふらつく「浮動性のめまい」について
カラダがフワフワとふらついて頭痛やしびれを伴ったり、歩くことが困難になるめまいを「浮動性のめまい」と呼びます。
浮動性めまいは急に発症したり、または徐々に症状が現れる場合もあります。
脳の異常で起こることが多いです。
★クラッとする「立ちくらみ」について
立ち上がった時にクラッとしたり、目の前が急に真っ暗になり、ある時は失神を起こしてしまう立ちくらみ。
これは、血圧の変動によって脳に送られる血液量が不安定になることで引き起こされます。
★眼精疲労からくる「視性めまい」について
視覚の異常を脳が受け取ると「視性めまい」を引き起こすことがあります。
視性めまいには、空間認識障害や強い光による衝撃などさまざまな要因があるとされたていますが、今回取り上げている眼精疲労も、視性めまいの大きな要因といわれています。
眼精疲労が慢性化して、血液の流れが悪くなる血流障害と重なることで、ふらつきやめまいを誘発しやすくなります。
眼精疲労によるめまいの改善策について
眼精疲労によるめまいは、カラダが悲鳴をあげているサインです。
パソコンを使ったデスクワークの多い方は、こまめに休憩をとりながら作業しましょう。
また、休憩の時には目をつぶって脳を休ませたり、可能な方は蒸しタオルなどで目を温めてあげるのも効果的でしょう。
パソコンに限らず、スマートフォンなどの使用も必要最低限に抑えましょう。
この他、ウォーキングや軽い運動を取り入れることで全身の血流が促進され、めまいを軽減することができます。
眼精疲労から起こる、めまいを引き起こしてしまう前に、日頃からこまめに目を労わり、休ませてあげることが大切です。
三半規管、脳、血圧、血流に影響を与えるカラダのゆがみが大元の原因となっていることも多いので、病院での治療でなかなかよい結果が出ていないのであれば、一度視点を変えて、カラダのバランスを整えていくことをお勧めします。
その結果、お薬でなかなか改善しなかった「めまい」が大幅に減少または、改善されたケースも整体を受けたられた方に多数おられます。
カラダのゆがみから起こる「めまい」なら川越総合整体院へ
(川越総合整体院)
2016年12月13日 08:50





川越市 新河岸の整体院 【眼精疲労からくる頭痛について】

眼精疲労からくる頭痛について、その特徴と対処の方法について、今回はお伝えしたいと思います。
ご参考下さい!
長時間のパソコン作業や読書などで、目を酷使した後に起こりやすい眼精疲労(疲れ目)。
目が乾く、ゴロゴロする、ピントが合わせにくいなどの症状が出ることが多いのですが、眼精疲労から頭痛が起こることもあります。
眼精疲労からくる頭痛の特徴と対処法について、痛みの感じ方や、痛みが続く時間などにそれぞれ特徴がありますので、ご自分の頭痛がどのタイプなのかチェックされるとよいでしょう。
眼精疲労が原因となる頭痛について
「緊張型頭痛」と「片頭痛」
一般的に慢性化するタイプの頭痛は、主に3つあります。
・緊張型頭痛
頭が締めつけられているように感じる頭痛です。
首や肩の筋肉の緊張によって起こることが多いので、首や肩に強いコリを伴うことが多くあるのが特徴です。
また、長期間にわたって痛みが続くこともあり、めまいや全身のだるさを伴うこともあります。
・片頭痛
個人差はありますが、月に数回の頻度で発作的に起こる頭痛です。
左右どちらか、または両側のこめかみのあたりがズキンズキンと脈打つような痛みを感じ、吐き気を伴うこともあります。
数時間から3日間程度続くこともあって、発症は男性に比べ女性に多いのが特徴です。
・群発頭痛
片頭痛や緊張型頭痛に比べてあまり知られていないタイプの頭痛ですが、痛みの強さは緊張型、片頭痛よりも強く、例えとしては目の奥をえぐられるように感じるなど、痛くてじっとしていられない状態などと、経験されたクライアントさんからお聞きします。
痛みは15分から3時間程度続くことがあります。
また、群発頭痛は、ひとたび起こると1、2カ月の間は、毎日のように痛みが起こるケースがります。
前述した3種類よ頭痛の種類の中で、片頭痛と緊張型頭痛については、眼精疲労から起こる可能性があります。
眼精疲労による頭痛の対処方法
頭痛の原因が眼精疲労である場合、目の酷使を避けることが大切です。
そのために、日常生活で心がけたいポイントをお伝えします。
◎ 近視や乱視、遠視のある人はその状態に適したメガネ、またはコンタクトレンズを使用し、楽に読み書きできるように最低40cmの距離を保つよう心がけましょう。
◎ 部屋の明るさに気をつけましょう。
読み書きをするのに暗い照明は禁物です。
逆に、明るすぎる直射日光の下でも目の負担は大きくなりますので注意して下さい。
◎ パソコン作業の際は、背筋を伸ばしたカラダに負担の少ない正しい姿勢で座るようにしましょう。
川越総合整体院では、負担の少ない座り方をしっかりアドバイスさせていただいております。
読み書きと同様に、目をディスプレイに近づけ過ぎるのも注意しましょう。
◎ 目を酷使するパソコン作業や読み書きの際には、1時間ごとに10~15分程度、目を休ませるようにしましょう。
このような日常生活や仕事のなかでできる予防策を習慣化するだけでも、頭痛の原因となる眼精疲労を大幅に軽減することができます。
もしご自身の取り組みでも、なかなか変化を実感できない眼精疲労には、カラダのゆがみが大きく関係しているかもしれません。
お一人で悩まず、まずは川越総合整体院にお気軽にご相談下さい。
(川越総合整体院)
2016年12月10日 07:03





川越市 新河岸の整体院 【眼精疲労による頭痛・肩こり】

眼精疲労による肩こりや頭痛のメカニズムと改善策について、お伝えしたいと思います。
眼精疲労による頭痛と肩こりは、放っておくと日常生活にも支障をきたしかねません。
早めの対策を、先ずはご自身で取り組んでいきましょう。
眼精疲労と肩こりは、どちらも筋肉への負担と血流不良で起こる症状です。
時には激しい頭痛を引き起こすこともあります。
眼精疲労による肩こりや頭痛が慢性的に起こっている方は、注意が必要です。
眼精疲労による肩こり・頭痛のメカニズム
私たちの目の周りには薄い筋肉が張りめぐらされています、目を酷使することひよって、この薄い筋肉に疲れとコリが溜まります。
このように目に疲れが蓄積されることで発生するのが、眼精疲労です。
さらにその疲労は、首を通って肩にまで影響してきます。
首から肩にかけての筋肉が緊張して血行不良となり、その結果、肩こりや頭痛が引き起こされてしまうのです。

放置すると日常生活に支障が?
眼精疲労から引き起こされる、肩こりや頭痛は集中力を低下させるだけでなく、精神的なストレスの蓄積にもつながります。
さらにその状態を放っておくと、筋肉に溜まった疲労物質が抹消神経を傷つけてしまい、ひどいと手のしびれや痛みを発症する可能性もあるのです。
眼精疲労による肩こりや頭痛を回避するには
日常生活で眼精疲労を予防するための対策をすることで、肩こりや頭痛をある程度は回避する事ができます。
まずは、自宅や職場のパソコン環境を見直してみて下さい。
ディスプレイやキーボードは、目の位置より少し下にくるように設置します。
デスクトップ、ノートの違いで高さを上記に近くなるようイスの高さなどを変えてみてください。
目線より高い位置にディスプレイがあると目が空気に触れる面積が大きくなって、目が乾きやすくなり、その分負担がかかりやすくなります。
イスの形状としては、猫背を予防するために背中のカーブに沿ったものを選び、正しい姿勢をキープしやすくしましょう。
そして自宅であれば、部屋の照明は、白熱灯にすると目の負担を軽減させることができます。
さらに長時間パソコン作業を行う時は、1時間に最低1回は休憩をとるようにします。

その際に、軽いストレッチやセルフマッサージなどをして、筋肉の緊張をほぐしてあげることで、眼精疲労による肩こりや頭痛をある程度は防ぐことができます。
このように、簡単な改善または予防策を習慣に取り入れるだけで、眼精疲労を緩和させたり防ぐことは可能です。
ぜひ、日常生活に取り入れてみて下さい。
ご自身での取り組みで、なかなか良くならない眼精疲労への整体なら→川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年12月 6日 08:05





川越市 新河岸の整体院 【眼精疲労の症状と原因】

今回は、眼精疲労の原因と症状について、お伝えしたいと思います。
もしあなたが、長引く目の疲れを感じているのであれば、眼精疲労の可能性があります。
改善のためにも、ご参考いただき、原因を特定していきましょう。
仕事でもプライベートでもスマホやパソコンの多用によって目を酷使し「目が疲れる」「目が痛い」という悩みを抱えている人が、増えています。
睡眠や休養をとることで症状が少しは落ち着くことはあっても、一向に改善しない場合は眼精疲労を疑ってみるとよいでしょう。
眼精疲労は単なる目の疲れと違い、放っておくと頭痛や肩こり、めまい、吐き気などの症状が現れることもあります
。
眼精疲労の主な原因
目のトラブルから起こる場合
近視、乱視、老眼が進むと、ピントを合わせるために眼球の内部で水晶体の厚さを調節する筋肉の緊張が続きます。
また視力の低下によって目を凝らしたり、顔を前に出すなどの姿勢が増えることで、目の疲れや肩こりが生じやすくなります。
特に40代半ば過ぎから急速に進む傾向にある老眼が、眼精疲労の大きな原因となっていることも。
さらに、めがねやコンタクトレンズが合わないために眼精疲労が起きることもあります。
ご自身で取り組むこととしては、定期的に検査を受けるなどをして、目に合ったものをするようにしましょう。
ドライアイ
パソコンなどで目を酷使する人がなりやすい、眼球の表面が乾燥する病気です。
目を保護する役割のある涙の減少や、涙の質が低下することによって、目の表面に傷ができてしまいます。
そのため、目の疲れやすさや、乾燥以外にも痛みや不快感、まぶしさを感じることがあります。
さまざまな目のトラブルが、やがて眼精疲労の原因になります。
身体のトラブルから起こる場合
風邪やインフルエンザなどで体力が低下している時も、眼精疲労の症状があらわれることがあります。
また耳や鼻の病気、更年期障害や自律神経失調症、低血糖、糖尿病、脳の障害などの病気も眼精疲労を引き起こすと言われています。
生活環境から起こる場合
はじめにもお伝えしたように、パソコンやスマートフォンの普及により、仕事でもプライベートでも長時間にわたって目を酷使する機会が増えていて、眼精疲労に与える影響も大きくなっています。
精神的ストレス(自律神経の乱れ)
ストレスが高まると不安感やイライラなどの精神的な影響だけでなく、高血圧や血行不良をはじめとした身体的な影響も出ることがあり、眼精疲労もその症状のひとつです。
複数の原因が重なって起こる場合
このように眼精疲労には上記したようなことが大きな原因として考えられるのですが、このうちの1つだけが原因の場合は、目の疲労は起きても眼精疲労まで起こすことは少ないでしょう。
いくつかの原因が重なることで目の負担が増え、眼精疲労になるのです。
ですから眼精疲労を治していくには原因のひとつひとつを見極めて、それぞれについてのケアや生活習慣を改善するなどの対応をしていく必要があるのです。
川越総合整体院では、原因となるカラダのゆがみを整え、目の負担を低減させて回復をサポートします。
自律神経の乱れから起こる場合も、当院の得意とする分野だと自負しております。
お気軽にご相談下さい!
川越市 新河岸の カラダの歪みから起こる「痛み・こり・しびれ」専門の整体院 川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年12月 3日 07:05





川越市 新河岸の整体院 【足がつるのを予防する】

寝ている間に足がつる経験をしたことは、一度はあるのではないでしょうか。
なかには足がつることが慢性化して頻繁に起きる人もいます。
そうならないための、予防セルフケアについてお伝えしたいと思います。
ご参考下さい!

くり返す足のつれ、どうすればいいの?
一度足がつると、頻度に個人差はあるのもも、クセのようになってしまう人もいます。
年齢を重ねるにつれて、足がつる症状が慢性化するという場合もあります。
もしあなたが、最近、足がつる回数が増えているなぁ〜と感じているのでしたら注意が必要です。
夜中などに繰り返し起きたりすることで睡眠不足になったり、つれた時に筋肉を痛めてしまい、筋肉痛が残ってしまい生活しづらくなったりすることもあるからです。
では、今回のテーマであるくり返す足がつれ(こむら返り)を予防するために、まずはご自身でケアしていただく方法についてお伝えします。
足がつる(こむら返り)の現象は、一度クセになってしまうと何度も起きてくり返すことがあります。
そうならないためにも、日頃から予防の為のセルフケアをしておくことをオススメします。
また昼夜を問わず、頻繁に足がつるという場合には糖尿病や肝硬変、腎不全、椎間板ヘルニアなどの病気が潜んでいることもあります。
どうしても改善しないという人は、病気がそうさせているの可能性がありますので、様子をみ過ぎたり、自己判断はせずに、まずは病院から受診してみましょう。
検査の結果、特に異常が見当たらない場合、病院ではあまり重要視されていないカラダのゆがみから頻繁している可能性もあります。
そんな時は、川越総合整体院にご相談下さい。

足がつる(こむら返り)の予防方法
頻繁に足がつることが起きる場合には、慢性化させないためにも日頃から、以下のような予防の為のセルフケアを行ってみましょう。
ストレッチ・セルフマッサージ
運動が好きな人も、そうでない人にも有効的なストレッチや自分でするマッサージです。
ふくらはぎを手で軽く揉んだり、筋肉に沿って手をすべらせたりしてマッサージすると、日常生活で蓄積される筋肉の疲れの回復促進がされます。
足や全身の筋肉を、適度に伸ばすストレッチと一緒に習慣化することで足がつるのを予防できます。
足の筋肉を刺激す
足の筋肉を適度に動かして刺激し血行を促進させることです。
下半身の筋肉を動かして刺激するには、スクワット運動は足の筋肉を効率良く動かすことができる運動で、血流が良くなることから疲労回復に繋がるでしょう。
膝を曲げ伸ばしするだけの簡単な動きなので、すぐに誰でも実践できます。
ただし、ゆっくりやると意外と疲れるものなので、リズミカルに、回数は慣れてきたとしても、多くて1日の中で複数回のセットにわけて、トータルでも100回程度にして、あまり疲れを溜めすぎないようにしましょう。
食生活を見直す
あなたのカラダを構成している大元は、あなたの摂る食事から成り立っています。
ですので、食生活の見直しも大事です。
食事は栄養バランスを重視して、特にミネラルが不足しないように心掛けることが大事です。
ミネラルのうち、筋肉の動きに密接にかかわるカルシウムやマグネシウムは特に積極的に摂り入れましょう。
カルシウムは小魚や乳製品に多く含まれていて、マグネシウムはナッツ類や大豆製品などに多く含まれています。
無理なく毎日摂取できるものばかりなので、続けるようにしてください。
食事での摂取が難しい場合は、サプリメントから補助的に摂取するのでもいいでしょう。

日頃からできる運動前後の予防策
運動不足にならないために、毎日運動をしているという人は、運動中や運動後に足がつるのを避けるため、次のことに気をつけるといいでしょう。
運動前はしっかりとストレッチしたり、軽くウォーミングアップをしてから運動を始めることがポイントです。
運動中は血液中のミネラルバランスが崩れないように、水よりもスポーツドリンクを飲むようにすると良いでしょう。
ただしスポーツドリンクは糖分も多いので、飲み過ぎには注意して下さい。
糖尿病や肥満が懸念される場合には摂取量などを十分に考える必要があります。
運動後は疲労を溜めないため、軽目のセルフマッサージやストレッチを行っておけば万全です。
カラダのゆがみから起こる「足のつれ・こむら返り」なら、川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年11月29日 08:21





川越市 新河岸の整体院 【妊娠中に足がつる原因について】

妊娠中期から後期にかけて、寝ている時などに足がつる(こむら返り)ことが多くなります。
今回は、妊娠中に起きる足がつる(こむら返り)原因について、お伝えしたいと思います。
ご参考下さい!
妊娠中に足がつる原因
妊娠中は、足がつる(こむら返り)がよく起きる傾向にあります。
特に妊娠中期くらいから起きやすいようです。
お腹が大きくなるにつれて、その頻度は増えていきます。
夜、寝ている時などに突然起きることが多く、毎晩足がつるという人もいます。
ではなぜ妊娠中は、頻繁に足がつるのでしょうか。
夜中、布団の中で足がピーンと張って痛い思いをしたという妊婦さんは多いと思います。
この足がつる現象は妊娠中に起きやすいのですが、原因としてお腹の中の赤ちゃんが、妊娠中期以降それまでよりも一気に大きくなることが多く、それにつれて体重も増え、妊婦さんの足の筋肉に負担がかかってくることにあります。
また、お腹がさらに大きくなれば下半身を圧迫し、どんどん下半身へのの血流が悪くなってきます。
そのことによって、お腹が大きくなる妊娠中期くらいから症状が出てくることが多いのです。
カルシウム・マグネシウム不足、冷えなどが原因の場合も
このように足がつる直接的な原因は、お腹が大きくなることによる血行障害が主に考えられるわけですかが、間接的には筋肉疲労やカルシウム・マグネシウム不足、冷えも関係していることもあります。
特にカルシウムに関しては筋肉や神経の働きにとても重要な役割を担っています。
またマグネシウムも同様に筋肉の働きを調整したり、筋肉痛を緩和したりしてくれています。
これらのことから、筋肉を正常に働かせるためには、血液中のカルシウムとマグネシウムのバランスが大切になってきます。
そして、このバランスが崩れ始めると、筋肉に異常をきたしてしまいます。
カルシウムやマグネシウムの豊富な食材には、イワシやサバなどの魚、ひじき・わかめ・こんぶなどの海藻類などを意識的に摂るようにしましょう。
最後に、冷えも足がつる原因となる1つです。

妊娠中はとくに、足を表に出すような服装を避けて、下半身や足を冷やさないようにすることを心掛けましょう。
普段、家にいる時も足元は冷えやすいので、ひざかけなどを使うことをオススメします。
カラダの歪みから起こる「痛み・こり・しびれ」専門の整体院 川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年11月26日 07:46





川越市 新河岸の整体院 【急に足の指がつれる原因】

ふくらはぎがつれることは多くの人が一度は経験されたことがあるでしょう。
しかし、つれる場所は様々で、足の指がつれてしまう人がいます。
例えば、寝ているときや足の指だけを動かしたときなどに、足の指がつることがあります。
では、この足の指が急につる原因は、どこにあるのでしょうか。
今回は、足の指が急につる原因についてお伝えしたいと思います。
「足の指がつれて気になっている」という人は、ぜひご参考にしてみてください。
足の指がつるってどういう状態?
普段歩いたり運動したりしているとき、もしくは夜、布団に入ってから睡眠中などに足の指がつることがあります。
自分の意志とは関係なく、足の指が硬直してまわりの筋肉が収縮し、痙攣(けいれん)状態になります。
また多くの場合、筋肉の異常収縮によって痛みを伴います。
足の指がつる原因
足の指がつるのは、運動不足のときや、普段しないような動きをしたときに起きやすくなります。
原因として考えられるのは、運動不足や、筋肉疲労、筋肉に対する強い刺激、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分の不足、筋肉の冷えなどです。
それぞれの原因について詳しくお伝えしていきたいと思います。
足の筋肉の疲れ
運動をして足の筋肉を使うと、体内では急速にカルシウムやナトリウムなどのミネラル分が消費されていきます。
運動を続ければ、筋肉疲労が進み、さらに足や足の指がつりやすい状態になります。
体内のミネラルバランスの乱れ
運動中に水分が不足し、脱水症状が起きると、体内のミネラルバランスが崩れます。
そうすると、従来の筋肉や神経の動きを調整するミネラルの働きが乱れて、筋肉が異常な状態になり、痙攣などを起こすと考えられています。
特にカルシウムやマグネシウム不足が原因であると言われています。
足の筋肉の冷え・血行不良
これからの時季に注意が必要ですが、カラダの冷えは、筋肉の冷えにつながって、血行不良を引き起こします。
そうすると神経の働きが鈍低下して、足の指がつるのではないかと言われています。
何らかの病気のサイン?
足の指のつれには、時に病気が潜んでいる場合もあります。
日に何度も足の指がつるのであれば、まずは医療機関を受診しましょう。
足の指がつるという何気ない現象も、カラダが異常を知らせてくれているサインかもしれません。
ゆっくり休息する、睡眠不足の人は改善する、食事の栄養バランスを意識するなど生活習慣の見直しをしましょう。
カラダの歪みから起こる「痛み・こり・しびれ」専門の整体院 川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年11月24日 07:50





川越市 新河岸の整体院 【足がつる原因はカラダの不調?】

足がつる(こむら返り)のは、カラダの不調を知らせるサインである事があります。
今回は、足がつる原因やその理由についてお伝えしたいと思います。
夜中寝ているときに突然足がつることがあります。
突然のことに、何が起きたんだ!と驚いてしまいますが、あなたのカラダが不調を訴えていることがあります。
足がつる場合、その原因を考え、ご自分のカラダが今どのような状態なのかを確認しましょう。
「足がつる」原因について
足がつることには、いくつかの原因が考えられます。
主に以下のような原因が考えられます。
筋肉の疲労
一番多いと言われている原因です。
筋肉の酷使によって疲れが溜まることで、神経系統との連携がとれなくなり、筋肉が収縮してしまいます。
電解質バランスの乱れ・栄養不足
電解質のバランスとは、筋肉や神経の動きを調整している血液中のミネラルバランスが乱れると、筋肉の興奮状態である痙攣(けいれん)が起きます。
カルシウムなどのミネラルが筋肉の収縮や弛緩といった運動信号の役目を果たしているからと言われています。
運動不足、加齢による筋肉量の減少や血行不良
運動不足や加齢、疲労、冷えによる血行不良などが原因で、温度調整機能が低下することによって、筋肉の伸び縮みがうまく制御できなくなるというものです。
特に睡眠中に足がつるという場合には、これが原因であることが多いです。
また、疲労が蓄積したり、カラダゆがみがあったり、自律神経のバランスが乱れている場合にも、筋肉の機能低下や血行不良によって、連れやすくもなります。
原因となる疾患について
椎間板ヘルニアや糖尿病、動脈硬化などの疾患が「足がつる」原因であることもあります。
カラダの不調を知らせている?
栄養不足や血行不良などが重なり、また急激な運動などで筋肉疲労が起きると、足がつることが起こりやすくなるのです。
足がつる = 病気では必ずしもありません。
なんの病気にもなっていない健康な人にもしばしば起きうるもので、極端に心配することはないでしょう。
しかし、頻繁に起きる場合は、カラダが何らかの不調を知らせるサインとして出している可能性があります。
日に何度もつれるような場合は今回の記事を参考に、原因を突き止めそれに応じて、まずは病院を受診して医師の診断を受けることが大切です。
特に異常が見当たらなくて、様子を見てもなかなか改善されない場合は、カラダのゆがみや、自律神経のバランスの乱れから起こっているのかもしれません。
そのような時は、川越総合整体院の整体があなたのお役に立てることでしょう。
お気軽にご相談下さい。
カラダの歪みから起こる「痛み・こり・しびれ」専門の整体院 川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年11月21日 08:07





川越市 新河岸の整体院 【足がつる①症状】

足がつる(こむら返り)→急に痛みを伴って足の筋肉が縮んだり、痙攣(けいれん)を起こしたりする症状です。
大概の人は経験あると思います。
冬場もつれやすくなりますので、参考にしていただき、対処や予防に取り組んでみて下さい。
今回は、足がつる(こむら返り)の症状が起きる部分や起きやすい時などをお伝えしたいと思います。
足のつれ(こむら返り)は、特に疲れが溜まっている時や寝ているときにふくらはぎがギューっと固くなって、痛みを伴いしばらく足を動かせなくなります。
つまり、足がつった状態のことですね。
「足がつる」とは、筋肉が急にギューっとに縮んだり、痙攣(けいれん)したりすることで、非常に強い痛みを伴うこともあります。
足がつる(こむら返り)の症状
急に強い痛みを伴って、自分の意志とは関係なく、足の筋肉が収縮したり、痙攣(けいれん)したりするのが、足がつったときや、こむら返りが起きたときの症状です。
人よっては、しびれを感じることもあり、筋肉が固くなって動かしづらくなります。
足がつる(こむら返り)が起きやすい部分
よく足がつれる部分は、ふくらはぎにでしょう。
足の側面や足の指などにも起こります。
また、足がつることを「こむら返り」とも呼びますが、この「こむら」とは「腓」と書き、「ふくらはぎ」のことを指すのです。
こむら返りは足だけでなく、手や首、おなか、背中など筋肉のあるところなら、どこにでも起こり得ます。
足がつる(こむら返り)が起きやすいとき
足がつる(こむら返り)は、足を激しく動かす運動中などに起こりやすいです。
激しい運動をすると、筋肉に疲労物質が溜まることで、筋肉の興奮が起きるためだとも考えられています。
その他、ジョギング、ハイキング、ウォーキングなどの軽い運動のときでも起きることはあります。
このような場合、準備運動が不足やしていなかったり、普段使っていない筋肉に急に力を入ることが原因として考えられます。
睡眠中や布団に入っているときなどにもよく起こります。
不意にやってくる、足のつり(こむら返り)てすが、初めてのときはびっくりするかもしれません。
また、対処法がわからず、ひたすら痛みをこらえながら治まるのを待つという人もいますが、対処方法についてもお伝えしていきたいと思います。
次回は足がつる(こむら返り)の原因についてお伝えしたいと思います。
カラダの歪みから起こる「痛み・こり・しびれ」専門の整体院 川越総合整体院
(川越総合整体院)
2016年11月19日 07:35





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。